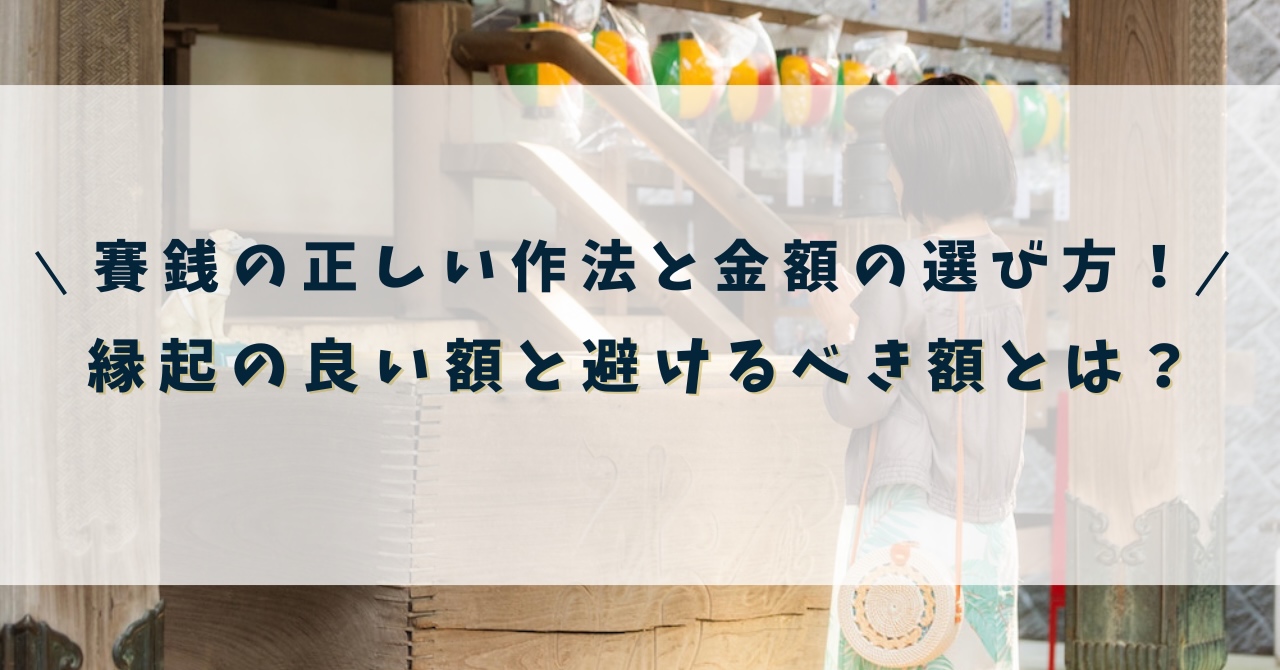A子
A子お賽銭はいくら入れるのが正解なの?



お賽銭はなんのためにするのだろう?
お寺や神社を訪れた際に、こうした疑問を抱いたことはありませんか?
この記事ではお賽銭の正しい作法や、縁起の良い金額の目安を禅宗僧侶の資格を持つ私が解説します。
お賽銭はただお金を入れるだけではなく、正しい意味や作法を理解することでより良いご利益を得られるとされています。
記事を読むことで、より心のこもったお参りができるようになるでしょう。
お寺や神社での賽銭の歴史と意味


賽銭の起源は米などの供物
お賽銭の起源は、神仏への感謝の気持ちを示すために供えられた供物にあります。
古代の日本では、海の幸や山の幸が神仏に捧げられ、その中でも特にお米は重要なお供え物とされていました。
お米は白紙に包まれて「おひねり」として供えられることもありましたが、貨幣制度の発展とともに、米の代わりに金銭を納めるようになります。
江戸時代の1700年頃にはすでに賽銭箱が存在し、貨幣の普及とともに現代のようにお賽銭を納める習慣が定着しました。
賽銭の目的は神仏への感謝を伝えること
お賽銭の本来の目的は、神仏への感謝を伝えることにあります。
古くから日本人は日々の暮らしや収穫に感謝し、神仏にお供えを捧げてきました。
農耕民族であった日本人にとって収穫物を神に捧げることは、翌年の豊作を願う重要な行為でした。
現在でもお賽銭は「神仏に願いを叶えてもらうための対価」ではなく、「感謝を示すもの」として納めることが大切だとされています。
またお賽銭には以下のような意味があります。
- 自分についた穢れをお金に移し、それを神仏に納めることで身を清める。
- お賽銭を入れる音で、参拝へ来たことを神仏に知らせる。
(しかし全ての神社やお寺でこの考え方があるわけではないので、基本的には静かに入れるようにしましょう。) - お寺では「お布施」としての意味もあり、煩悩を捨てる修行の一環である。
お寺や神社で賽銭を入れるときの正しい作法


賽銭を入れる前の準備と心構え
お賽銭をする前に、まず心を整えます。
お金を投げ入れるのではなく、丁寧に納めます。
とくに寺院では、静かに参拝することが望ましいでしょう。
また賽銭を入れる際には「自分が何を願うのか」や「何に感謝するのか」を明確にすることが大切です。
ただお金を入れるだけでなく、心を込めたお参りをしましょう。
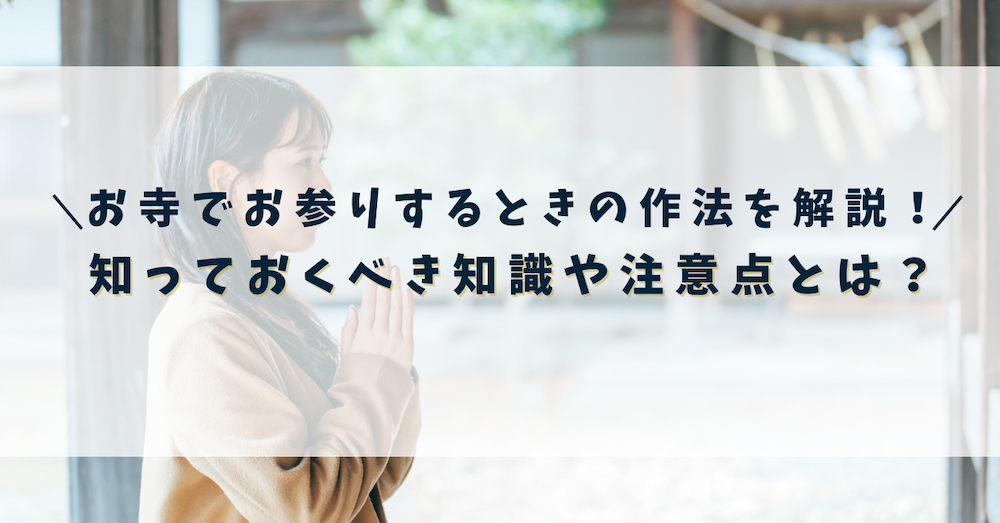
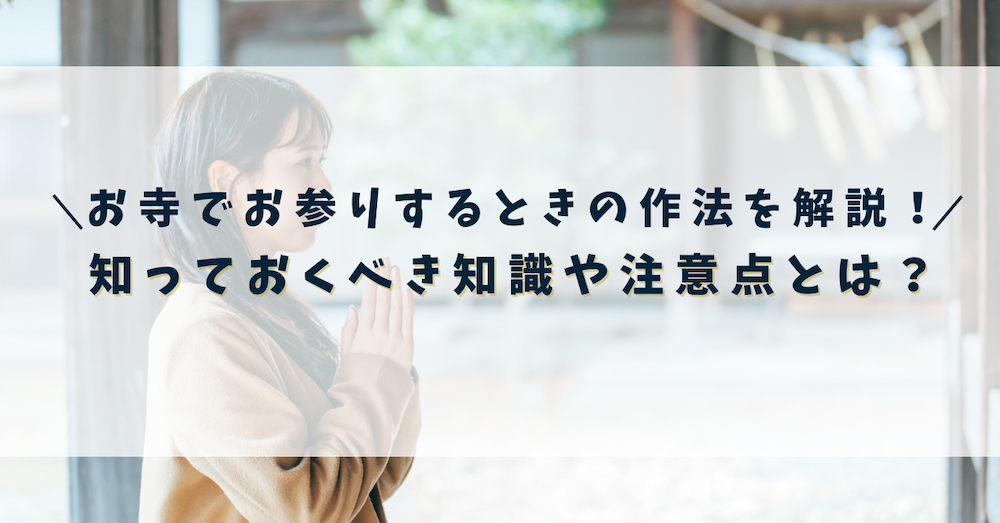
賽銭は丁寧に入れましょう
お賽銭を入れる際は投げ入れるのではなく、そっと箱の中に納めるようにします。
とくに寺院ではお賽銭は「捧げるもの」とされるため、静かに入れることが望ましいでしょう。
神社の場合も本来は静かに納めるのが理想ですが、賽銭箱によっては投げ入れるようになっているところもあります。
賽銭で縁起の良い金額と悪い金額


縁起が良いとされている金額
お賽銭の金額にはとくに決まりはありませんが、縁起を担ぐために語呂合わせを意識して金額を決める人が多いです。
一般的に縁起が良いとされている金額は以下のものです。
- 5円(ご縁)
- 15円(十分なご縁)
- 25円(二重のご縁)
- 115円(いいご縁)
- 125円(十二分なご縁)
- 415円(よいご縁)
語呂合わせの種類はさまざまですが、5円を基準にすると覚えやすく参拝時にも思い出しやすいでしょう。
なお実際に最も多く納められている金額は100円程度で、次いで5円、10円、50円が多いようです。
縁起が悪いとされている金額
一般的に縁起が悪いとされている金額は以下のものです。
- 10円(遠縁)
- 33円(散々)
- 65円(ろくなご縁がない)
- 75円(何のご縁もない)
- 85円(やっぱりご縁がない)
- 95円(苦しいご縁)
また500円玉は硬貨の中で最も高額であることから、「運が頭打ちになる」といわれることもあります。
しかしこれらはあくまで縁起を担ぐための考え方なので、必ずしも気にする必要はありません。
お賽銭として不要な小銭を処分する気持ちで納めたり、他人から借りたお金を納めたりすることも良くないとされています。
お賽銭は神仏への捧げものなので、小銭の処分や借りたお金で済ませるのではなく感謝の気持ちを込めて納めることが大切です。
賽銭に関するよくある疑問


賽銭は多ければ多いほどご利益がある?
お賽銭の金額が多ければ、その分ご利益が大きくなるというわけではありません。
お寺や神社にとってお賽銭は、境内の維持や運営のために役立てられます。
しかしそれ以上に大切なのは参拝する人の誠意や心です。
たとえ高額なお賽銭を納めたとしても、そこに感謝の気持ちや誠意がなければ形式的な行為になってしまいます。
金額の多さにこだわるのではなく、自分の気持ちに合った額を選びましょう。
小銭とお札はどちらが良いの?
小銭でもお札でも問題はありませんが、お札を使う場合はできるだけ綺麗なものを選び丁寧に納めましょう。
大切なのは金額ではなく、感謝の気持ちを込めることです。
小銭でもお札でも丁寧に扱い心を込めて納めることで、より意味のある参拝となります。
お寺や神社を訪れる際は、その時の状況や気持ちに応じてふさわしいお賽銭を選ぶと良いでしょう。
まとめ【賽銭は神仏への感謝の気持ち】
お賽銭は単にお金を納める行為ではなく、神仏への感謝の気持ちを表す大切な風習です。
その歴史を知り正しい作法を意識することで、より心のこもったお参りができます。
金額に決まりはありませんが語呂合わせなどを参考にしながら、自分の気持ちに合った額を選ぶと良いです。
お賽銭は「願い事の対価」ではなく「感謝の表れ」であることを忘れずに、より丁寧な参拝を心がけましょう。